Contentsベーネベーネのコンテンツ
最新記事一覧
-
# イベント情報銀座サロン

2025.06.01
【随時更新】ベーネ銀座サロン イベント情報
ベーネ銀座サロン 営業時間 月曜定休 営業時間 火曜日~土曜日 10:00~19:00 …
read more
-
# イベント情報銀座サロン

2024.07.20
◆銀座サロン 営業のご案内
銀座サロンのイベントスケジュールの確認が可能です。
read more
-
# 宝石の基礎知識

2025.07.11
【地金買取キャンペーン 7月25日~31日 買取金額の5%をさらにキャッシュバック】ベーネ銀座サロンの地金引き取りは、弊社にしかできない5つの大きなメリットがあります!
ベーネ銀座サロンでの地金買取、他社とは違う5つの大きなメリット。 古物取り扱いの免許を持つベーネで…
read more
-
# イベント情報

2025.07.10
【ベーネ大阪リアルショップ開催 7月18日(金)~20日(日)世界でたった一つだけのジュエリーを創る
【ご予約特典 オーダー15%off 旧品番ルース20%off!】 ご予約特典として、フルオーダージ…
read more
-
# イベント情報銀座サロン

2025.07.02
オレゴンサンストーン 鉱山主 新作ベアストーンコレクション販売会 美 眩いばかりの光、吸い込まれるような透明感。7月5日(土)11:00~15:00
高精密度を持つ最新テクノロジーの宝石研磨機を使い、研ぎ澄まされた感性と感覚が重なり、出来上がる至高…
read more
-
# イベント情報銀座サロン

2025.07.02
【ベーネ福岡リアルショップ開催 7月4日(金)~5日(土)世界でたった一つだけのジュエリーを創る
【ご予約特典 オーダー15%off 旧品番ルース20%off!】 ご予約特典として、フルオーダージ…
read more
-
# イベント情報

2025.07.02
あなたが選ぶ“1滴”が、あなた自身を整える。【フレグランス作成ワークショップ】あなただけの香りを創る特別な時間
身も心もあわただしく、せわしく揺れ動き、心柱のありどころをどこかに置き忘れているような、そんな日常…
read more
-
# イベント情報銀座サロン

2025.06.24
「まずはお見積りだけしてみようの会」6/25(水)~6/29(日) 開催
何かジュエリーが欲しいなぁ、と思ったときなんといっても心配なのはお値段 ましてや、自分の好みに合わ…
read more
-
# ジュエリーライフレシピ銀座サロン
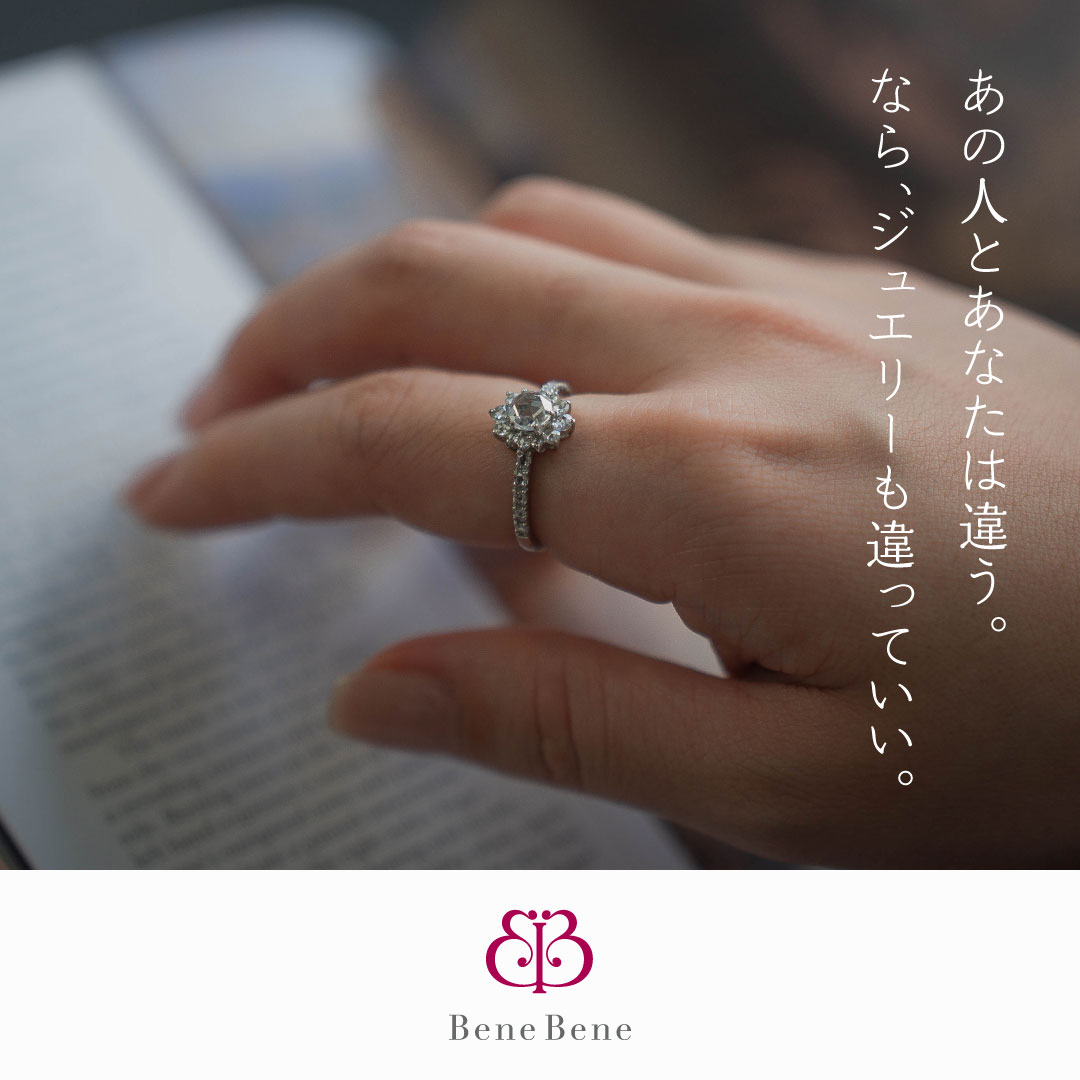
2025.06.21
世界でひとつだけのジュエリーを創る dizionario dei gioielli オーダージュエリーガイドブック完成 お申込みはこちらから。
世界に1つだけのジュエリーは、意外なほど、あなたのそばにあります。ベーネ銀座サロンのオーダージュエ…
read more
-
# イベント情報

2025.06.18
展示会出店Infomation
Bene Beneは展示会にも出店しています 各地で盛り上がりを見せている宝石の展示会。Bene…
read more
-
# イベント情報

2025.06.18
8/23(土)開催 ベーネ御徒町ルース販売会 あなたの欲しい、探している宝石にきっとここで出会えます。
7月は大阪でイベントを行っているため御徒町ルース販売会はお休みとさせていただきます。 あなたの欲し…
read more
-
# イベント情報

2025.06.14
Diamond Pierce Fair 6.20Fri-22Sun
いつかは欲しいダイヤモンドの一粒ピアス 存在感のある一粒ダイヤモンドのスタッドピアス。いつかは手に…
read more
-
# イベント情報

2025.06.14
その採集率は養殖真珠の1-2% 真珠を極めるとここに辿り着く<ケシ真珠フェア>6月28日(土)
私たちの日常は、自然界に現れる豊かな線に包まれています。ベールのように私たちを包み込む光。清らかに…
read more
-
# イベント情報

2025.06.04
【ベーネ横浜リアルショップ 6/6~7開催】
【ベーネ横浜リアルショップは6/6~7の2日間開催】 毎回大変好評いただいております、ベーネ横浜リ…
read more
人気の記事
-

2025.06.01
【随時更新】ベーネ銀座サロン イベント情報
# イベント情報銀座サロン
-

2024.07.20
◆銀座サロン 営業のご案内
# イベント情報銀座サロン
-
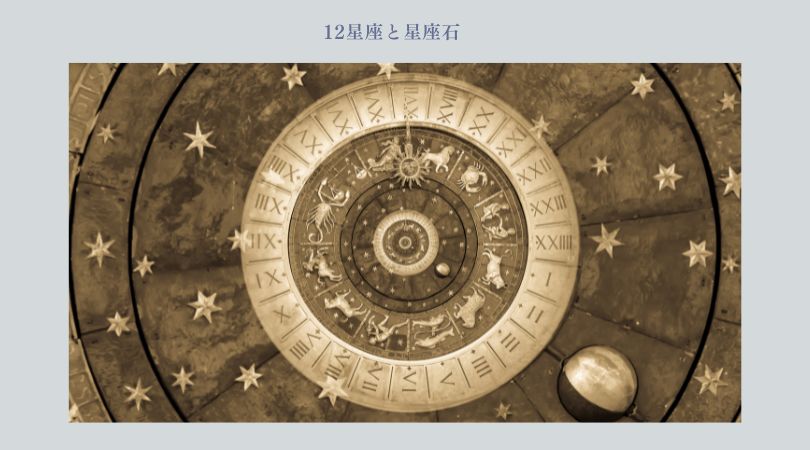
2024.03.14
【星座石は運命の宝石】十二星座と星座石
# 宝石の基礎知識
-

2024.03.26
【ベーネ ジュエリー美術館 2022年4月】図録掲載作品 詳細一覧
# 銀座サロン
-

2024.03.13
【星座石は運命の宝石】星座と宝石の不思議で素敵な関係
# 宝石の基礎知識
-

2025.06.04
【ベーネ横浜リアルショップ 6/6~7開催】
# イベント情報
-

2025.06.18
8/23(土)開催 ベーネ御徒町ルース販売会 あなたの欲しい、探している宝石にきっとここで出会えます。
# イベント情報

