Contentsベーネベーネのコンテンツ
最新記事一覧
-
# イベント情報銀座サロン

2025.12.07
【随時更新】ベーネ銀座サロン イベント情報
ベーネ銀座サロン 営業時間 月曜定休 営業時間 火曜日、木曜日、土曜日 11:00~19:00…
read more
-
# イベント情報

2025.12.21
展示会出店Infomation
Bene Beneは展示会にも出店しています 各地で盛り上がりを見せている宝石の展示会。Bene…
read more
-
# イベント情報

2025.12.21
55年の歴史を誇る老舗卸が一般開放!2026年最初の開催!1月18日限定「ベーネ御徒町ルース販売会」、あなたの理想の一石に出会えるチャンス
東京・御徒町──色石卸として業界55年の「ベーネユナイテッド」が、普段は業者のみ入場可能な“ルース…
read more
-
# イベント情報

2025.12.07
【期間限定キャンペーンのお知らせ】12月9日(火)~21日(日)地金買取金額の【5%】をキャッシュバック
切れてしまったチェーン、片方なくしてしまったイヤリング、デザインが古くなって使わなくなったジュエリ…
read more
-
# イベント情報

2025.12.05
お手持ちのジュエリーが劇的に変わる!ベーネ銀座サロン×彫り職人<川口和寿>スペシャルコラボ 池袋ミネラルマルシェ12月13日(土)、14日(日)
地金感を持つジュエリーは、川口氏の彫り細工で劇的に変わります。 今回の池袋ミネラルマルシェでは、ベ…
read more
-
# 銀座サロン

2025.12.04
【ベーネ ジュエリー美術館 2025年4月】図録Vol.8掲載作品 詳細一覧
【ジュエリー美術館】図録Vol.8April 2025 BeneBene 2ページPt900リング…
read more
-
# イベント情報

2025.11.02
【Bene Jewelry美術館 November 2025】11月14日(金)スタート
2025年11月14日、ベーネジュエリー美術館スタートです。展示されるすべてのジュエリーは、202…
read more
-
# 銀座サロン

2025.10.29
お二人の想いを永遠に刻む、世界にたった一組の結婚指輪 Bene 銀座サロン Marriage Ring
— 彫り職人・川口氏 × BENE(ベーネ)が贈る特別なリング — 結婚指輪は、ふたりの想いを永遠…
read more
-
# イベント情報

2025.10.29
言葉にできないことを表現する。言葉でない言葉で語る。千年の雅が令和に息づく ― 源氏物語 五四帖ベーネジュエリーコレクションご予約スタート
源氏物語は、言葉がつむぐ物語。その源氏物語を、言葉ではない、もしかしたら言葉では表すことのなかった…
read more
-
# デザインルーツ

2025.10.24
Bene 銀座サロン Engagement &Marriage Jewelry世界でたった一組のブライダルジュエリー。
ベーネ銀座サロンからご提案する世界でたった一組のブライダルジュエリー。婚約、結婚指輪は、一生身に着…
read more
-
# イベント情報

2025.10.23
お待たせしました!ベーネ銀座サロン福袋スタート。10月24日~11月30日(日)まで
えっ、もう福袋?!そうなんです。 2026年を、ピカッピカのジュエリーでお迎えいただきたくて。 ジ…
read more
-
# イベント情報
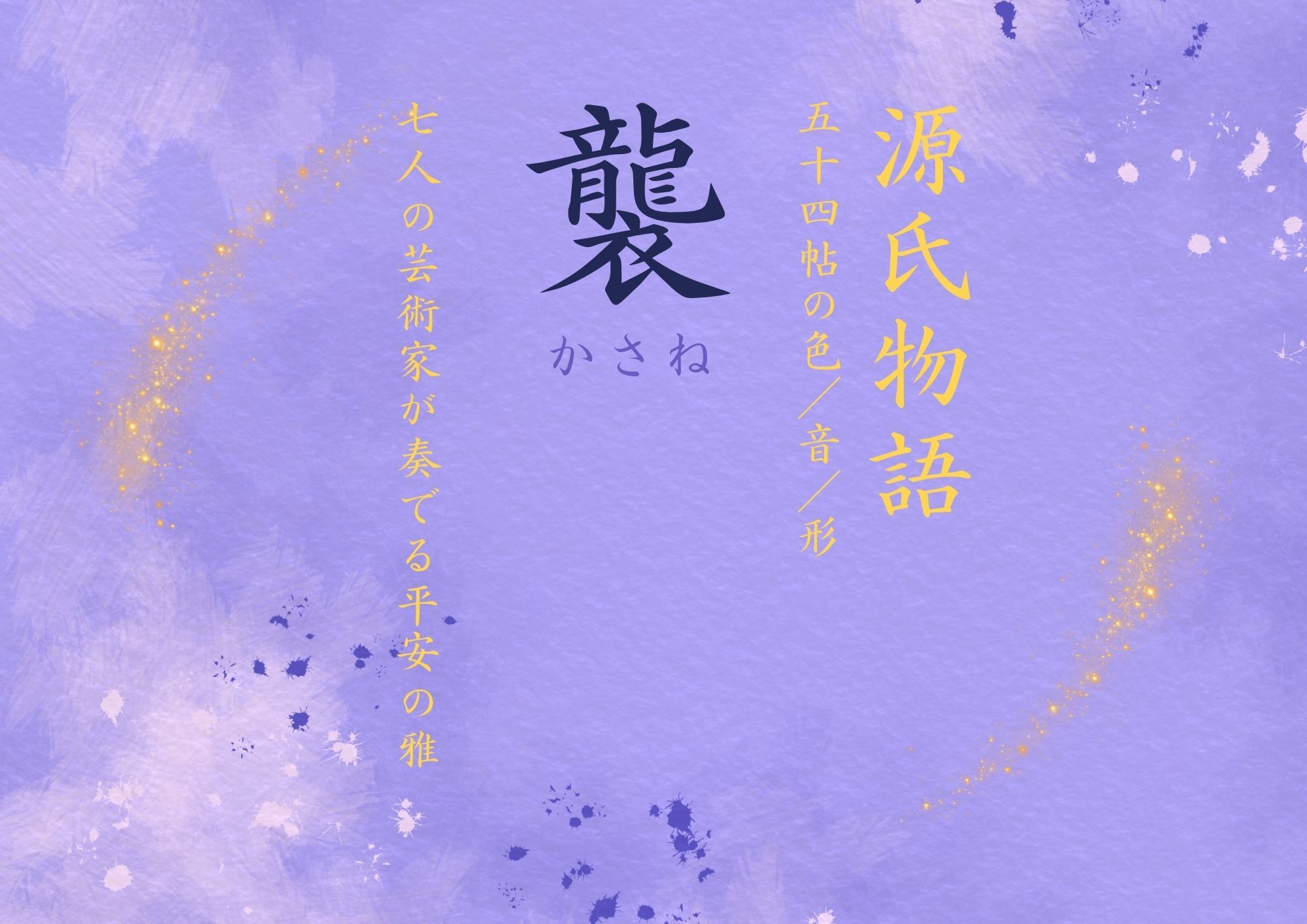
2025.10.12
千年の雅が令和に息づく ― 「源氏物語 五四帖の色、音、形 襲 KASANE」開催のお知らせ11月3日(月.祝日)
七人の芸術家が奏でる平安の雅 千年の時を超えてなお読み継がれる古典文学の金字塔『源氏物語』。この普…
read more
人気の記事
-

2025.12.07
【随時更新】ベーネ銀座サロン イベント情報
# イベント情報銀座サロン
-

2025.12.21
55年の歴史を誇る老舗卸が一般開放!2026年最初の開催!1月18日限定「ベーネ御徒町ルース販売会」、あなたの理想の一石に出会えるチャンス
# イベント情報
-
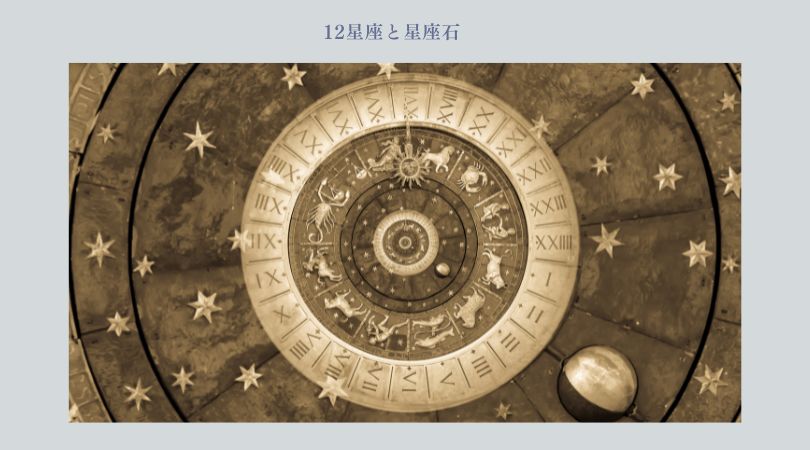
2024.03.14
【星座石は運命の宝石】十二星座と星座石
# 宝石の基礎知識
-

2024.03.13
【星座石は運命の宝石】星座と宝石の不思議で素敵な関係
# 宝石の基礎知識
-

2024.03.26
【ベーネ ジュエリー美術館 2022年4月】図録掲載作品 詳細一覧
# 銀座サロン
-
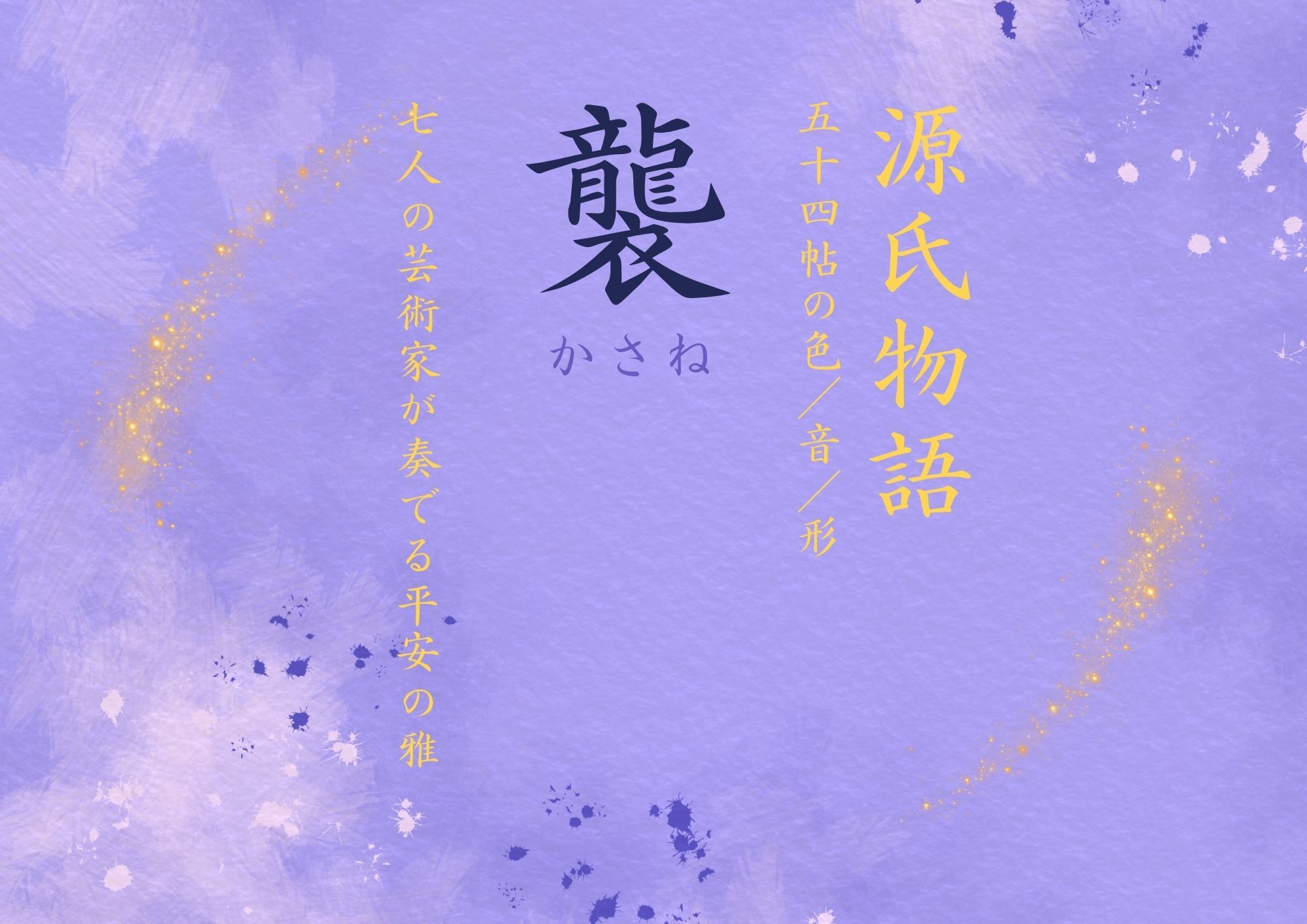
2025.10.12
千年の雅が令和に息づく ― 「源氏物語 五四帖の色、音、形 襲 KASANE」開催のお知らせ11月3日(月.祝日)
# イベント情報

